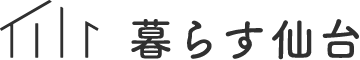投稿者: KRT
あたごのまつ酒ケーキ
雪室熟成珈琲ギフト
だだちゃ豆パスタ
有限会社玉谷製麺所
「だだちゃ豆パスタ」
有限会社玉谷製麺所は仙台市産業振興事業団が主催する、新東北みやげコンテスト受賞企業です。

昭和24年(1949)、月山のふもとで産声をあげた「有限会社玉谷製麺所」。創業から60年、そばの栽培が盛んな山形で、そばやうどんを丁寧に作り続けています。
そんな老舗の製麺所で2018年に誕生したのが、「だだちゃ豆パスタ」です。

開発を担当した玉谷貴子さんは「弊社は、製麺所としてこれまでにもいろいろなパスタを作っているのですが、この『だだちゃ豆パスタ』の前年にさくらんぼのパスタを作ったところ、地元のみなさんにすごく喜ばれたんです。だったら、山形のものを使ったほかのものを作れたらいいなって」と、開発のきっかけを話してくれました。
食材に選んだのは、庄内地方で作られている在来種のだだちゃ豆。

「ただパスタを作るだけじゃなく、プラスアルファがほしいと思って。山形は米どころでもあるので、玄米を使ったパスタにしようと。それだったら、小麦アレルギーのある人も食べられる!っていう発想だったんです」と話します。

写真:玉谷製麺所の工場。きわめて高い技術力は、業界内でも評判です
小麦を使ったパスタの製造はお手の物ですが、玄米を原料にするパスタは、いつもの勝手とは全く違いました。

写真:玉谷製麺所の工場内。そばは一晩、パスタはその2倍の時間をかけて、じっくり低温乾燥させます。この丁寧な仕事こそが、玉谷製麺所の麺のおいしさの秘密
「まず、パスタの形にならないんです。形が壊れてしまったり、そもそもおいしくない。それで、山形県の加工品の研究センターに相談して、8ヶ月くらいかけて試行錯誤を重ねました」。解決のヒントをうかがうと「うーん。これって企業秘密になるのかしら・・・」と笑いながらも、「米とだだちゃ豆の粉を混ぜるときに湯捏ねしたんです。そうしたら、形も美しく、だだちゃ豆の素材力が引きだせて、すごくおいしくなったんですよ」と教えてくれました。

写真:かわいらしい形も、玉谷製麺所のパスタの特徴です
さやと2粒の豆のかわいらしいパスタの形状も、玉谷さんのアイディアです。実は、山形在来作物案内人でもある玉谷さん。この山形在来作物案内人というのは、山形大学農学部の講座を受け、在来作物やその知識を活用する人材のこと。玉谷さんは「山形に残るだだちゃ豆も、在来作物として残していかなくてはいけないもののひとつです。今回のパスタを作るにあたっては、おいしさだけではなく形もしっかり受け継いでいきたいと思いました。なのでまずはさやの形。あとは、だだちゃ豆の最高品質である“さやの中の2粒の豆”。それでさやの形と豆2つの形になったんです」と話します。
このユニークな形を生み出す金型は、イタリア製。100kg以上の圧力をかけて生地を押し出し、だだちゃ豆パスタが成型されます。
だだちゃ豆がたっぷりなので、「パスタを茹でている最中にだだちゃ豆を茹でているような香りがするんですよ。サラダにしたり、素揚げにして召し上がっていただくのがおすすめです」と、玉谷さん。

写真:だだちゃ豆パスタアレンジレシピ。「だだちゃ豆とエビのペペロンチーノ」。かために茹でただだちゃ豆パスタに、玉谷製麺所オリジナルの「ガーリックソース」を絡めた一品。ソースは、オンラインショップで購入できます。
玉谷製麺所でこうしたユニークなパスタが誕生したのは、東日本大震災を機に、東北芸術工科大学のプロジェクトに参加したのがきっかけでした。
「東北の元気を世界に届けたい、と生まれたのが雪の結晶パスタ。豪雪地帯であるこの地域で、『雪が食べられたらいいのにね』なんていう話から生まれたんです」。

その後、大ヒットとなったのが「サクラパスタ」。玉谷さんは「サクラパスタは、冬場に売れるんです。どうやら縁起物、合格祈願として使っていただいているようです。そして、日本のシンボルでもある桜のパスタを作れるのは、世界中見渡しても弊社だけ。ということで、今はシンガポールや韓国、アメリカにも輸出しているんですよ」。

写真:サクラパスタアレンジレシピ「合格サラダ」。好きな野菜に茹でたサクラパスタをトッピング。鮮やかな色合いの人参ドレッシングでいただけば、明るい春を予感できるハッピーな一皿に
鮮やかでかわいらしいピンク色は、ビーツによるもの。「添加物は使いたくないし、でも天然のものでピンク色が出せなくて困ったなぁっていうときに、農家さんから『不揃いでどうしようもないビーツを、なんとかできないか』とご相談いただいて。今では山形県産で追いつかないところまできていて、国産のビーツも使用しています。今、山形でも生産量拡大しているので、そのうち山形県産だけで賄えるようになると期待しています」と話します。

写真:大ヒット商品となった「サクラパスタ」とニューフェイスの「だだちゃ豆パスタ」「ローズパスタ」。今後東北みやげとして多くの人たちに愛される存在になりそうです
最新の商品は、ハートの形がかわいらしい「ローズパスタ」です。そしてこの商品の誕生も、地元農家からの相談がきっかけでした。
「無農薬栽培で育てている農家さんでバラのソースを作ったりしていたのですが、なかなか販路が広がらないということで。『パスタにできない?』という相談がきて、やってみたんです。口に入れてすぐにバラの香りがする香料入りのものはありますが、このパスタはしばらくしてからふわっと薫るんですよ」。

写真:ローズパスタをかために茹でて、バニラアイスクリームのトッピングに。ふんわりバラが香る、ちょっと贅沢なデザートに変身!
この「ローズパスタ」は村山市のバックアップも受けています。村山市が「東京2020」でブルガリアのホストタウンとなっていることから、「ブルガリアの人たちにも食べてもらおう!」という話もあるのだとか。パスタもバラも、ハートがかわいいのも世界共通ですから、きっと気に入ってもらえることでしょう。

写真:玉谷さんおすすめの「素揚げ」にして軽く塩とブラックペッパーを振りかけます。香ばしくて、ビールのおつまみにもピッタリ!
次々とユニークなパスタを生み出す玉谷製麺所。これから先、どんな商品を生み出していくのでしょうか。玉谷さんは「東北の方々に支えられながらやってきた製麺所ですので、東北の素材を使ったパスタを考案中です。今は畑のものを使っているけれど、今度は海のもの。東北は広くて、おいしいものがたくさんあるので、考えるだけでワクワクするんですよね」と、楽しそうに話します。
「このパスタは、私たちができることがいろいろあると気づかせてくれたんです。それに、『玉谷製麺所にこんなのがあったらいいね』と夢を語ってくれるお客様が増えて。夢を託してもらえるようになったのはすごく素敵なことだと思うんです」。
東北の人たちのさまざまな想いを形にしたパスタは、これからも日本、そして世界に「おいしい!」を届けていくことでしょう。
有限会社玉谷製麺所
住所:〒990-0701 山形県西村山郡西川町睦合甲242
フリーダイヤル TEL:0120-77-5308
(受付時間 AM9:00-PM5:30)
通常ダイヤル TEL:0237-74-2817
(受付時間 AM9:00-PM5:30)
フリーダイヤル FAX:0120-77-5506
(受付時間 24時間)
URL:https://www.tamayaseimen.co.jp/wp/

醤油チーズフロマージュ
ほやチーズ
いちじく甘露煮 山ぶどう仕立て
八戸サバ缶バー
株式会社マルヌシ
「八戸サバ缶バー」
「株式会社マルヌシ」は仙台市産業振興事業団が主催する、新東北みやげコンテスト受賞企業です。

青森県八戸市は、全国有数の水揚げを誇る港町。なかでも、秋に八戸港に揚がる八戸前沖さばは、脂の乗りがよく、とてもおいしいと評判です。そんな八戸前沖さばを使用した新しい八戸土産「八戸サバ缶バー」を開発したのが、地元の新鮮な魚介を加工販売している「マルヌシ」です。

開発担当者は「八戸前沖さばは、毎年秋の限られた時期にのみ八戸港に揚がるサバで、ものすごく脂がのっていておいしい。この前沖サバを使って八戸の新しいお土産を作りたいと思ったのが、開発のきっかけです。だって、これまでどこかに行くときに手みやげ持っていこうと思っても、結局手にするのが青森県内の別の地域で作られているリンゴのお菓子だったりしたんですよ。八戸の人たちが誇れる『これぞ八戸!』というものを作りたかったんです」と話します。

写真:マルヌシの主力商品であるシメサバの製造工程。人の手できちんと成型しています

写真:シメサバの製造工程。成型したサバを塩水で洗っています
開発には、青森県が中心となって行っている加工品相談会を利用しました。マルヌシにとっては、土産品の開発は初の試みで、1年ほどの期間を費やしたといいます。「弊社は、シメサバを主力商品にしているのですが、シメサバで使用するサバは大~中サイズ。近年サバが小型化していく中で、小サイズのサバをどうにか活かしたいという思いもありました」と話します。

こうして生まれたのが「津軽海峡の塩」「ゆずこしょう」「グリーンカレー」「アヒージョ」「トムヤムクン」「ハバネロ」という、6種類のフレーバーの「八戸サバ缶バー」。

写真:八戸サバ缶バーのアヒージョ味。この澄んだタレと一緒にパスタと和えれば一品完成!
「うちは完全に後発だったので、いまさらサバの水煮や味噌煮を出しても埋もれてしまう。だったら、とにかくいろんな味を出そう、と。本当は8種類くらい出したかったんですけれど、2018年3月の時点で出せるクオリティのものが6種類になったんです。パッケージに関しては、コンセプトを土産と決めていたので、地味にしたら埋もれてしまう。なので、カラフルにして目立つように。ネーミングに『バー』と名付けたのは、BARでいろんなお酒が並んでいるように、いろんな味が並べば楽しいなという思いでつけました」。
ポップでかわいらしいデザインは、地元八戸のデザイナーによるもの。
素材も、加工も、パッケージデザインも“オール八戸”で臨んだ、「これぞ八戸!」な土産品の誕生です。

現在は、そこにもう1種類、青森県民の“ソウルフレーバー”と言っても過言ではない「スタミナ・源たれ」味を加えて7種類のフレーバーを販売。「スタミナ源たれになったのは、単純に『スタミナ源たれ味だったらうまいだろうな』って思ったから(笑)。今後は、中国韓国系が足りないので、そちらを検討しようと思います。2020年3月の発売に向けていろいろ考えているんです」。

写真:マルヌシ工場のみなさん。八戸サバ缶バーを手に笑顔!
この「八戸サバ缶バー」が買えるのは、青森県内のお土産店と県外の青森県アンテナショップのみ。ネット販売などは行っていません。
「いつでもどこでも手に入る時代に抗っています(笑)。こんな便利な世の中ですけど、青森でしか買えない商品がひとつくらいあってもいいのではないかな、と思うんですよね」。

写真:八戸サバ缶バーアレンジレシピ「ハバネロ味のピザ」。
ピザ生地にプチトマト、ハバネロ味八戸サバ缶バー、チーズを乗せて焼くだけ。仕上げにバジルを散らせば、白ワインにピッタリのピリ辛ピザの出来上がり!

写真:八戸サバ缶バーアレンジレシピ。「ヘルシースタミナ定食」。
スタミナ源たれの味の八戸サバ缶バーと適量のキャベツ、もやし、ニラを炒めるだけの簡単料理ながら、抜群のおいしさ。玄米、お味噌汁と合わせれば、ボリューム満点ながらヘルシーな定食に!
これからも新たな味わいを加え、「八戸サバ缶バー」を発展させていきたい、と話す開発担当者。「地域で愛されている調味料や料理とコラボするのもいいなと思いますね。いずれ、当社の看板商品になってくれたら・・・と思います」。
自社の看板商品、そしていずれは八戸土産といえば・・・!という存在になるべく、「八戸サバ缶バー」はますますの進化を遂げていくに違いありません。
株式会社マルヌシ
〒031-0821 青森県八戸市白銀二丁目5-1
TEL:0178-33-1571 FAX:0178-34-6305
URL https://www.marunushi.co.jp
取扱店舗情報 https://www.marunushi.co.jp/38canbar/
※「八戸サバ缶バー」はネット販売を行っておりません。上記の取扱店舗情報をご確認ください。

撮影/堀田 祐介
東北大学法学部卒業後、仙台市内の商業写真撮影会社に就職。写真の道に進む。アシスタントを経てカメラマンとなり、物撮、人物撮影など、写真全般にわたり様々な仕事をこなしながら10年勤務。その後準備期間を経て独立、現在はフリーランスとして、プロバスケットボール・仙台89ERSオフィシャル(初年度から現在まで。来季で15季目)のほか、雑誌媒体の取材(街ナビプレス・仙臺いろはマガジン・ウォーカー・るるぶ)、商業写真撮影、番組用写真撮影と各方面で活躍。