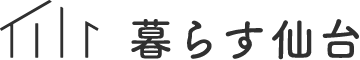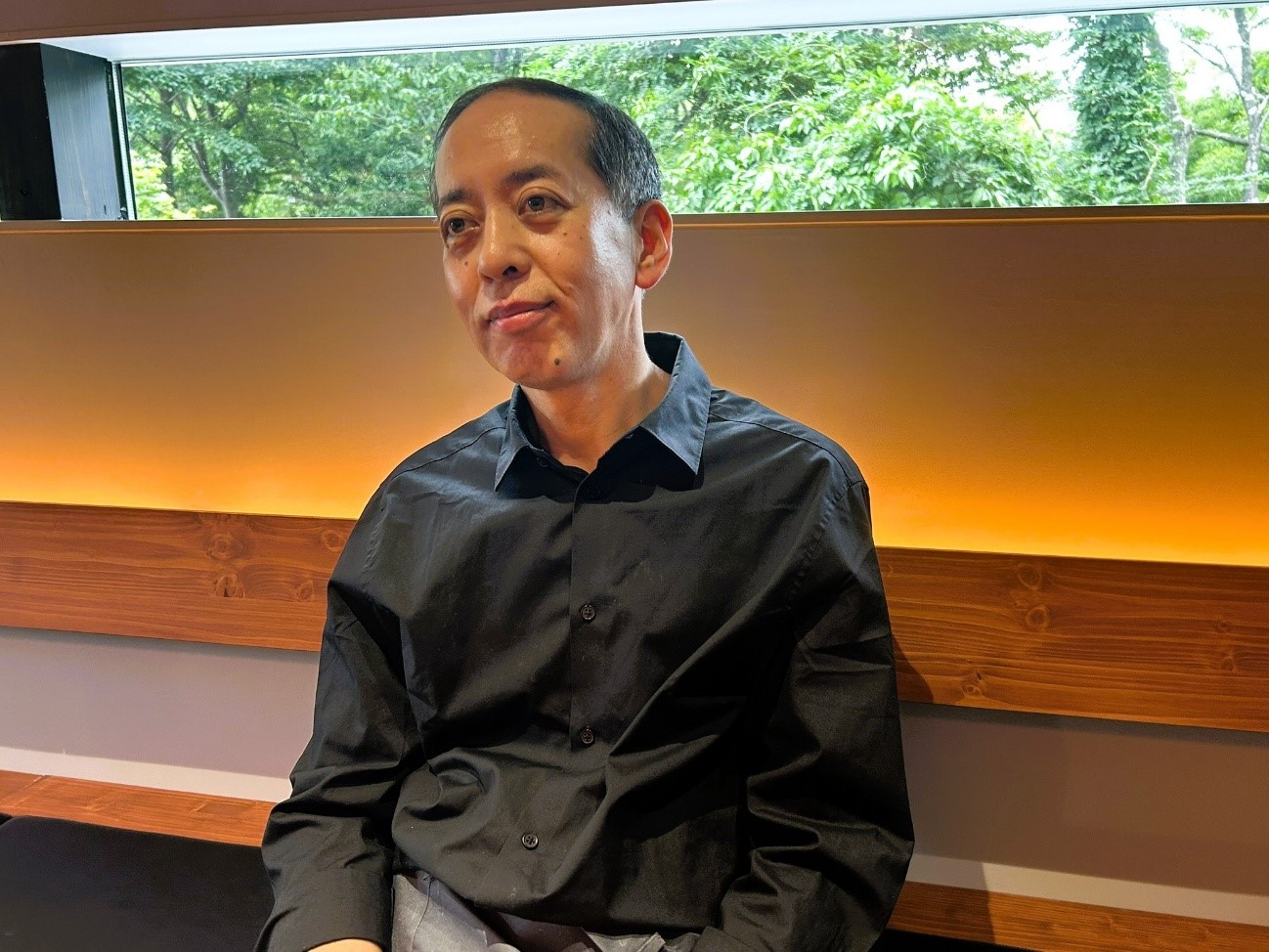株式会社ノルテカルタとは、仙台市産業振興事業団が主催する
第11回新東北みやげコンテストの受賞企業です。
秋田県の数ある名産品の中でも、「きりたんぽ鍋」などに欠かせない調味料が「しょっつる」です。
主にハタハタなどの魚を塩漬けして発酵させたもので、石川県の「いしる」や香川県の「いかなご醤油」と並び、日本三大魚醤のひとつといわれています。
魚のうま味が凝縮されたこのしょっつるで味付けされたのが、新東北みやげコンテストで地域性特別賞を受賞した「しょっつるナッツ」です。

写真:株式会社ノルテカルタ代表の岡本さん
ノルテカルタの代表である岡本大介さんは、「もともとその僕らのところで、オイル漬けのチーズを作ったんですけど、その時に燻製チーズとアーモンドを入れたいねという話になりまして。それで、『アーモンドにしょっつるで味を付けてみよう』と、つくってみたんです。そしたら、気がついたらそのしょっつる味のアーモンドをずっと食べていて(笑)。止まらない感じだったんですよね。それで、『じゃあもうこれをそのまま出そう』って言って、商品化することになったんです。そもそもきっかけというか、構想自体はもう5年前ぐらいにはあったんですよ」と教えてくれました。
ノルテカルタの商品開発は「スピンオフ的に誕生している」と話す岡本さん。
「最初は、いぶりがっことチーズのオイル漬けをつくったんです。そうしたら『チーズ、おいしいね』ってみんなに言われて。それで、チーズのオイル漬けをつくることにしたんです。そのチーズは塩糀としょっつるで味付けしたんですけど、別バージョンで燻製チーズのオイル漬けをつくろうとなって。ただ、燻製チーズにその味付けをするのはどうだろう…ということで、アーモンドに味付けして入れちゃおうってなったんですよ。そしたらそのアーモンドがおいしかったっていう(笑)」

写真:風光明媚な秋田県八峰町で生まれた「しょっつるナッツ」
そして、この「しょっつるナッツ」を新東北みやげコンテストに出品。結果、地域性特別賞の受賞につながりました。
「受賞したことで、バイヤーさんに話しやすくなりました。こういった冠をいただけるのはありがたいですね」
商品開発にあたるのは、岡本さんと女性スタッフの方。
「だいたい僕が『こういうのって、どう?』って言うと、『何を考えてるの?』って言われながら(笑)、形にしてくれるんです。現在は、この『しょっつるナッツ』のフレーバー違いを開発中とだけ、お伝えしておきます」と、岡本さんは話してくれました。

写真:ビールがグイグイ進みます
今後の展望について伺いました。
「何種類かを集めてギフト用にすることを考えています。あと、サンプルを配ったときに、スナックやバーの方から『味がしっかりしているから、お酒に合う。業務用にしてくれない?』と言っていただいただけましたし、先日は某有名ホテルの方から『うちのバーでも出せたらいいね』と言っていただけたので、今後業務用の展開も考えていけたら」と、岡本さん。

写真:はちみつをとろりとかければ、赤ワインにぴったりなおつまみに
一度手を出したら止まらなくなる“悪魔の美味”な「しょっつるナッツ」は、東北スタンダードマーケット(仙台市)やオンラインストアで購入可能です。ビールやワイン、お気に入りのお酒と合わせて楽しんでみては?

写真:レタスなどの野菜に「しょっつるナッツ」と粉チーズでパワーサラダに

写真:田子ガーリックマヨネーズで味付けしたパンプキンサラダに「しょっつるナッツ」をトッピング。絶品です

写真:バニラアイスにトッピング。甘じょっぱくて、最高の味わいです
岡本大介さんのこれまでのものがたりは、Yahoo!ニュースでご紹介しています。ぜひご覧ください。
株式会社ノルテカルタ
所在地 〒018-2664 秋田県山本郡八峰町八森古屋敷18
TEL 0185-57-3444
FAX 050-3201-4427
URL https://www.nortecarta.com/