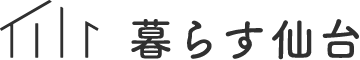投稿者: KRT
石巻うまいもの株式会社
「石巻金華茶漬けシリーズ」
石巻うまいもの株式会社は、仙台市産業振興事業団が主催する、新東北みやげコンテストの受賞企業です。
日本有数の水揚げ高を誇る石巻漁港を有し、“魚の町”として知られる石巻市。2011年の東日本大震災で甚大な被害を受け、その復興の歩みの中で誕生した会社が「石巻うまいもの株式会社」です。

写真:石巻うまいもの株式会社が運営する「石巻うまいものマルシェ」。石巻市水産総合振興センター1Fにあります
2014年、石巻市内の水産加工会社を中心とした12社で「石巻うまいもの発信協議会」としてスタートし、高付加価値商品の開発やブランディングを行ってきました。3年の活動期間を経て、2016年、株式会社ヤマトミ、山徳平塚水産株式会社、湊水産株式会社、株式会社MCF、水月堂物産株式会社、株式会社丸平かつおぶし、株式会社カクト鈴木商店、末永海産株式会社、株式会社田伝むし、富士國物産株式会社の10社が手を取り、石巻ブランドの商材を扱う直営店の運営を開始。当初は直営店運営がメインでしたが、もともと高付加価値商品の開発を目指していたグループだったこともあり、「共同で新商品の開発をしよう」ということになったのだそう。
商品開発の陣頭指揮を執ったのは、商品部会長の丸平かつおぶしの阿部真也さんと山徳平塚水産の平塚隆一郎さんでした。

写真:(左から)丸平かつおぶしの阿部真也さんと山徳平塚水産の平塚隆一郎さん。丁々発止のやり取りをするおふたりは、なんと高校の同級生なのだとか
「10社それぞれ強みを生かした商品で、素材を活かしつつ常温で持ち歩けるものが条件。それでいろいろ話していくうちに、お茶漬けがいいんじゃないかという風になってね」と、阿部さん。平塚さんは「お茶漬けは10社中7社やっていて、レトルトの設備がない会社にはうちを使ってもらっているんです。設備投資をすると負担が大きいけれど、こうやって共同でやっているとそれぞれの会社の設備が使えるから便利なんですよ。将来的には、グループだけじゃなくて、ほかの石巻全部を巻き込みたいですね」と話します。それに阿部さんも「石巻全体を一個の工場にしたいよね」と笑顔をのぞかせます。

写真:自社のレトルト技術を活用して、「石巻金華茶漬けシリーズ」の開発を牽引した、平塚さん
港町ということで、震災前から多くの水産加工会社が立ち並んでいた石巻。こうして手を携える理由のひとつが「石巻ってこれっていう商材がないからなんですよ」と、平塚さん。「魚種が200種も揚がるから、人に『石巻って何があるの?』って聞かれると、『いろいろ・・・季節によってね・・・』なんて口ごもっちゃうくらい(笑)。商材がかぶるとライバルになるけれど、今ある10社中8社は業態が違う。さんま、ほや、海藻、たらこ・・・と、得意分野が違う。石巻の弱点でもあったところが有利に働いたんですね」。

写真:山徳平塚水産の工場内。このレトルト技術が、今回の商品開発で大きな役割を果たしました
こうして共同でお茶漬けの開発を始めることになりましたが「1食300円なんて売れるのか?っていうのが心配で。だから最初はうちと山徳さんで作って。銀鮭とさんまをセットにして販売してみたら、6000個売れたんですよ。『これだったらいけるかも』ってなったら、ほかの会社も乗り気になってきて(笑)」と、阿部さん。

写真:「1食300円のお茶漬けが売れるのか心配だった」と話す阿部さん。現在、丸平かつおぶしが開発した「石巻銀鮭茶漬け」は、JAL国際線日本発ビジネスクラスの「2食目のアラカルト」に採用されるまでに!
連携して作る最初の商品ゆえ、失敗できないというプレッシャーの中、平塚さんと阿部さんはサンプルを東京に持って行き、各ジャンルの専門家のアドバイスを仰いだそうです。「2日間、30人くらいの方々と意見交換させてもらって。でももう1日目でけちょんけちょん(笑)。今のデザインになる前だったんだけど、『味はいいけど、よくわからない』って言われましたね(平塚さん)。
「ネーミングが『ほどるまんま』だったからね(笑)。これ、石巻の方言であったかいご飯という意味なんですね。方言を普及する意味でもいいんじゃない?ってうちらは思ったんだけど、みなさん曰く『方言の説明もしなきゃいけないし、なんの商品なのかもわからない』って」(阿部さん)。

写真:専門家の意見をもとに、パッケージデザインを大人向けの高級路線に
当初のポップなパッケージデザインを一新し、消費者の目線を大切にした高級路線に。ロゴマークには市の樹木である黒松と、石巻の象徴である金華山をモチーフに取り込みました。こうして、7社による7種類のお茶漬けと2種類のふりかけが完成しました。「それぞれの会社に販売チャネルがあったことと、『新東北みやげコンテスト』で特別賞を受賞したことで、売り込みやすくなりましたよね。商談のときは、自分のとこだけの商品を持って行ってもインパクトないから、他社のものも持って行くんです。すると、紹介したのに自社の商品が選ばれないっていう悲劇もたまに起こる(笑)」(平塚さん)。
統一ブランドで販売することで得た強み。阿部さんは「本音で言えるようになるまで3年かかりましたよね。これまでは『まぁ、いいんじゃないですか』って言ってたのが『これじゃ売れない』『もっとこうして』と、研鑽できる場になりました」と話します。

写真:「これからも、石巻から本物を届けたい」と話すおふたり。新作が楽しみです
現在は、第二弾として「釜飯のもと」を考えているそう。「我々の強みを生かして、本物を提供したいですよね。十三浜のわかめをスープにしたり、あとは魚醤もいいかな、と。輸出できていないほやで魚醤を作ったりとか。あとは、ほやのビスク。殻を使うんだけど、鮮度が命だから、ここでしかできない商品じゃないですか」と、平塚さん。

写真:石巻ならではの魚種の多さが幸いして、獲れる魚が変わっても問題ないとのこと
近年は、温暖化によって水揚げされる魚種も変わってきているといいます。「天然のぶりが三陸で揚がるようになったんですよ。ワタリガニが日本一獲れた年もあるし。それまで少量だった魚が主力になってきているのが現状です。魚種が変わってくると、我々も変わらざるを得ないけれど、石巻は200種以上の魚が揚がるのが特徴だから、その中身が変わるだけ」(平塚さん)。

写真:「石巻銀鮭茶漬け」。ゴロッとした切り身が入った贅沢な一品です

写真:「石巻さんま茶漬け」。骨まで柔らかくなった甘辛のさんまとお出汁の絶妙な組み合わせは、「ひつまぶし」を思わせる味わい

写真:「石巻さんま茶漬け」を、稲庭うどんと一緒に。ご飯だけじゃなく、うどんやそばなどと組み合わせてもおいしくいただけます

写真:「石巻ほや茶漬け」を茹でたパスタを和えれば、「簡単ほやパスタ」の完成!彩りに添えたバジルとほやの相性も抜群です

写真:この「石巻金華茶漬けシリーズ」は、高速道路のサービスエリアやJR仙台駅のお土産店のほか、「石巻うまいものマルシェ」で購入することができます
地の強みを活かしつつ、これからも「石巻うまいもの株式会社」はワクワクするような「食」を全国の食卓に届けていくことでしょう。第二弾、第三弾の発売が待ち遠しいのは、私だけではないはずです。
石巻うまいもの株式会社
(石巻うまいものマルシェ)
〒986-0022 宮城県石巻市魚町2丁目12-3
石巻市水産総合振興センター1階
※石巻市場前に無料駐車場あり
TEL 0225-25-4363
営業時間 日曜日 10:00~15:00
月曜日・水曜日~土曜日
9:00~16:30
定休日 火曜日
URL http://umaimono-ishinomaki.com/
第81回ジャパン・フード・セレクション食品・飲料部門グランプリ受賞(2024年11月)

-

- 三陸ホヤのキムチ漬
- 肉厚の三陸産ほやを、本格キムチに
-

- 乾燥納豆
- ポリポリです。納豆です
-

- 仙臺しそ巻(胡桃極)
- おいしく楽しい郷土料理
会津木綿coronイヤリング
くらをの米麹茶 缶詰め
合資会社羽場こうじ店
「くらをの米麹茶 缶詰め」
合資会社羽場こうじ店は仙台市産業振興事業団が主催する、新東北みやげコンテスト受賞企業です。
※現在、パッケージ・商品名をリニューアルして販売中!

写真:歴史ある酒蔵を改装してオープンした「旬菜みそ茶屋 くらを」。「勇駒」の看板が往時を偲ばせます
秋田県横手市。かまくらで有名な、雪深いこの土地で100年以上にわたって麹屋を営んでいるのが「合資会社羽場こうじ店」です。
この羽場こうじ店に生まれ育ち、現在市内中心部の増田町で「旬菜みそ茶屋 くらを」を営む鈴木百合子さんを訪ねました。「くらを」は、麹の食文化を広く伝えようと鈴木さんが2013年にオープンさせた食堂。併設されたショップでは、羽場こうじ店の麹のほか、この麹を使用した味噌などを販売しています。
情緒ある増田の通りにあって、ひときわ趣のある「くらを」。鈴木さんは、「この建物は、もとは江戸時代からお酒を造っていた酒蔵だったんです。平成15年に商いを閉じてしまったのですけれど、国の指定を受けている蔵が中にあるがために建物を取り壊すことができなくて。『誰か管理維持できないか』という話をいただいて、実家の麹屋で引き取らせていただいたんですよ」と、話します。

写真:「くらを」では、日替わりの定食のほか、甘酒や米麹茶の提供も行っています。増田町の蔵のある町並みを訪れたら、ぜひ「くらを」でランチ&ティータイムを楽しんでは
「くらを」で提供するのは、どこか懐かしい感じの食事。「都会の人たちには想像できないくらい、ここではお米を食べるんです。米中心の食文化だから、麹屋も珍しくない。横手って、人口が10万人いないのに、麹屋は23軒もあるの。今、日本中で発酵食品ブームだけど、横手ではずっとずっと昔から家庭に麹があって、発酵食品を食べる文化があったんです。だから、増田町で何をしたらいいだろう・・・って考えたときに、これだ!って思って。うちの商売をお伝えするのにいいと思ってここを始めたんです」と、とても楽しそうに話します。

写真:“女性が憧れる女性”といった感じの鈴木さん。都会からやってきたお客さんの人生相談に乗ることも度々あるとか
まさに秋田美人といった色白の肌に、つややかな輝き。鈴木さんの肌を見れば、麹の健康効果は一目瞭然。「見せられないのが残念だけど、私の腸って絶対きれいだと思う(笑)。一緒に働いている食堂のお母さんたちは、若くても60歳くらいなんだけど、本当、みなさんに彼女たちの肌を見てほしい。普段の食生活の結果がこうなんだから!って自慢したくてしょうがないの(笑)」。
麹のある生活を、多くの人に伝えたい-。常日ごろからそう考えている鈴木さんは、ある日、「麹そのものの抗酸化作用は過熱に耐えうる」という、専門家が寄せた一文を目にし、麹を乾煎りにしてみることに。「カラメルのような甘くて香ばしい香りがしてね。うわ、これはおいしそう・・・と思ってかじったら、固い(笑)。ポンポン菓子のようにはいかないか。じゃあ、水をかけたら戻るかな・・・って水をかけたら茶色い液体が出てきて。それを飲んでみたら、甘くておいしい!って(笑)」。これが、「くらをの米麹茶」の誕生の瞬間。「棚からぼた餅みたいな話でしょう」、そういって鈴木さんは豪快に笑います。

写真:「くらを」では、店頭で米麹茶を提供。ほっとした時間を過ごすことができます
出来上がった米麹茶を専門家に分析してもらったところ、「『麹の健康要素はないので健康茶ではないが、香りを楽しんでリラックスするためであればお茶といってもいいのでは』と言っていただいて。手間がかかるからビジネスにならないという人もいたけれど、それでもいいの。お茶にすることでとっかかりになってくれたらうれしいから」。ノンカフェインでシュガーレスなのにほんのり甘く、やさしい味わい。小さな子どもからお年寄りまで、楽しめるおいしいお茶の完成です。

写真:麹を丁寧にほぐしてから焙煎します。すべて手作業なので、大量生産をすることができません
自らの手で焙煎も行うため、一度にできる米麹茶の量はわずか。そのうえ「麹そのものが、ひいじいちゃんの製法で今もやっていて、機械で作るんじゃないの。だから一度で最高に作れて500kg。その中からこちらに譲ってもらえる量が少ないのと、焙煎に時間がかかるので大量生産できない。それに、原料の麹の出来も一定じゃないんです。生き物ですから。それを見極めるためにも、機械を使わずに自分の目で確かめながらじゃないと・・・」と、職人気質をのぞかせます。

写真:米麹茶は、普通のお茶のようにお湯で淹れても水出しでもおいしくいただけます。ほのかに甘い、やさしい味わいのお茶です
そして、「今の人たちって、疲れているでしょう。だからせめて一日に一回くらい、このお茶でホッとしてほしいなって思うんです」と、このお茶に寄せる期待を明かしてくれました。

写真:米麹茶にオレンジ、レモン、ミントなどを入れてフルーツフレーバーティーに。すっきりしていて、本当に美味!
ところで、「くらをの米麹茶」は、パッケージデザイン隆盛の昨今においては、驚くほどシンプル。「ベルリンに住んでる日本人の方がデザインしてくれたんです。いつもうちのことを気にかけてくださる方でね。私、このお茶が空港とかのお土産コーナーに置かれているのを想像したのね。あそこにガチャガチャしたデザインのものがあっても目立たないでしょう。だから、とにかく引き算でやろうということになって。それで、どうせだったら秋田の雪の色にしようって。実際に、サンプルを雪の上に置いてみて『まだ黄色い!』とかやって(笑)」。

写真:ドイツ在住のデザイナーがデザインしたパッケージ。潔いほどシンプルなデザインが目を引きます
パワフルで美しい鈴木さんに、今後の目標を伺いました。すると「麹屋に生まれて、この地域で育っていて、今は先輩方と一緒に働いていて学びがある。昔は日本のどこにもあった食文化がたまたま横手に残っていて、今ここって特別な場所になってるのね。だから、私はこの場所から、“かつて日本にあった食べ方の文化”を残していくのが義務だと思っているんです。麹の力を感じた自分が伝えられることがあると思うから、脈々とつながれてきた麹の力を活かした、それでいて現代の食卓にあった食べ方の提案をしていきたい。それはレシピ集だったり、教室だったり、イベントだったり・・・。いろいろな形でね」。

写真:これからも増田町から「麹のある生活」を発信し続けていく、という鈴木さん。次なるチャレンジが楽しみです
鈴木さんのミッションは、まだまだ道半ば。これからどんなことを仕掛けてくるのか、楽しみで仕方ありません。
合資会社羽場こうじ店
(旬菜みそ茶屋くらを)
〒019-0713 秋田県横手市増田町三又字羽場72
TEL:0182-45-3710 FAX:0182-45-3711
URL:https://kurawo.net/contents/
営業日 日~火・金・土
営業時間 10:00~16:00
ランチタイム 11:30~14:00
定休日 毎週水・木

撮影/堀田 祐介
東北大学法学部卒業後、仙台市内の商業写真撮影会社に就職。写真の道に進む。アシスタントを経てカメラマンとなり、物撮、人物撮影など、写真全般にわたり様々な仕事をこなしながら10年勤務。その後準備期間を経て独立、現在はフリーランスとして、プロバスケットボール・仙台89ERSオフィシャル(初年度から現在まで。来季で15季目)のほか、雑誌媒体の取材(街ナビプレス・仙臺いろはマガジン・ウォーカー・るるぶ)、商業写真撮影、番組用写真撮影と各方面で活躍。

メープルバウム会津桐
デザイン活用セミナー
受講者募集【終了】
デザイン活用セミナー開催!
「チラシもホームページも作ったけれど、集客につながらない」
「デザイナーに外注したいけど、予算が不安」
「起業はしたけれど、売上につながらない」・・・
そんな悩み、ありませんか?
セミナーに参加して、その悩みを解決するヒントを見つけてください。
(公財)仙台市産業振興事業団では「事例で解説!販促ツールのつくり方・使い方」と題し、3人のデザイナー、クリエイターが事例をもとに販促ツールに関する基礎知識をわかりやすく解説するセミナーを開催します。
日時:
2019年10月24日(木)
13:30-15:30
場所:
公益財団法人仙台市産業振興事業団 アシ☆スタ交流サロン
(仙台市青葉区中央1-3-1 AER 7F)
受講料:
無料(先着30名)
講師:
仙台市産業振興事業団
ビジネス開発ディレクター 佐藤 悠
クリエイティブ・プロデューサー 工藤 拓也
クリエイティブ・プロデューサー 岡沼 美樹恵
※申し込みは終了いたしました。たくさんのご応募、ありがとうございます。
福の小みやげ エゴマラー油
山形カクテルふるふる~ラ・フランス~
加藤嘉八郎酒造株式会社
「山形カクテルふるふるラ・フランス」
加藤嘉八郎酒造株式会社は仙台市産業振興事業団が主催する、新東北みやげコンテスト受賞企業です。
山形県鶴岡市。米どころであるこの土地で、明治5年(1872)創業の老舗の酒造があります。それが「大山」の名で親しまれている加藤嘉八郎酒造株式会社です。加藤清正の流れを汲む由緒正しきこの酒造は、鳥海山・出羽三山の伏流水と最上川の清流の恵みを受けた銘酒の数々を生み出してきました。

写真:「大山」の愛称で親しまれている加藤嘉八郎酒造
日本酒好きの間では、どちらかというと、硬派なお酒のイメージを持たれる加藤嘉八郎酒造で、日本酒以外で初めて開発に踏み切った商品が「山形カクテルふるふる」です。その誕生秘話を醸造担当の加藤嘉隆さんに伺うと、「きっかけは『山形カクテルミーティング』でした。これは『ゴッツォ山形』の佐藤智也氏と映画『よみがえりのレシピ』監督の渡辺智史氏が立ち上げ、3年連続で県のやまがた若者チャレンジ応援事業に採択された団体。山形の農家さんが後継者不足などの様々な問題により、果樹畑を伐採し、果物を廃棄しなければならない状況に追い込まれることもある中で、“単なるドリンクパーティではなく、生産者のお話を聞き、バーテンダーのオリジナルカクテルを楽しみながら、山形の果物の新たな可能性を皆さんと一緒に創りあげていこう”というものなんです」と、教えてくれました。

写真:醸造担当の加藤さん。実年齢よりも10歳以上は若く見える外見の秘訣を聞くと、「毎日の晩酌でしょうか(笑)」とのこと
もともと加藤嘉八郎酒造は山形カクテルミーティングのメンバーではありませんでしたが、「カクテルを作るときに、地の酒ということで大山のSAKEカクテルのベース用日本酒の『MOTOZAKE(基酒)』純米を使ってもらっていたんです。応援事業が終了した後、『山形カクテルミーティングの情報発信にも有効な商品を作ったらいいのでは』という話が持ち上がったそうなんです。そのときに、地元の山形地酒卸問屋の『株式会社武田庄二商店』さんを通じて、お話をいただいたのが商品開発のはじまりでした」。
カクテルのベースとなる日本酒は作っていたものの、リキュールの製造免許をもっていなかったため、加藤さんは少し躊躇してしまったのだそうです。しかしながら「お話を伺ったら、とても意義のあることだと感じたので、すぐにリキュール製造の免許を申請しました(笑)。その申請から始まり、『山形カクテルミーティング』さんと『株式会社武田庄二商店』さんと弊社で共同企画し、どういった商品を作ろうかという話し合いを重ねたんです」。

写真:加藤嘉八郎酒造の人気の酒。中でも高濃度仕込みの特別純米酒「十水」は、米のうま味がぐっと濃縮された銘酒。燗酒コンテストで最高金賞、ワイングラスでおいしい日本酒アワードでも2年連続最高金賞に輝きました
日本酒ベースのカクテルでありながら、今までにない商品。なかなかハードルの高いこの課題にヒントを与えてくれたのは、「山形の石焼き屋」さんとの出会いでした。「石焼き芋、焼きとうもろこしなどを作っているお店で、工房に石焼きプレートがあるんです。そこでは、農家さんから頼まれて、果物を石焼きにしてグラニュー糖を加えるだけの石焼きジャムも作っていて。ジャムなら甘みもあるし、果肉もあるから、これをカクテルにしたら面白いんじゃないかって思ったんですよ」。
これまでにない、という条件もクリアした石焼きジャムを使ったカクテル。しかも、ジャムとお酒を合わせたときに層になることから「カクテルシェーカーみたいにしようとか、どんどん話が広がっていきました」。

写真:高品質の酒が造れる自社開発した『OS タンク』。シャフトに四本の羽がついており、衛生的かつ均一に攪拌できるので、発酵のばらつきが少ないそう。蔵人は目で見て香りを嗅ぎ、もろみを管理。蔵人が判断したのちの攪拌は装置にまかせる。「大山」のおいしい酒の秘密は、職人の技プラス最新技術にありました
ところがここでひとつの問題が浮上します。「うちには酒の充填機があるけれど、ジャムの充填機はない。なので調べてみたら、高いんですよね。まだ形もない商品のために設備投資するのも難しくて・・・」。そこで加藤さんは、国のものづくり補助金への申請を試みます。「なんと採択されました!それで、補助金を利用してジャム充填機を購入したんです」。
こうして生産体制も整ったところで、加藤さんはレシピの最終的な仕上げをプロに依頼することに。「東京の銀座にある世界初の日本酒カクテル専門店『SAKE HALL HIBIYA BAR』を運営され、『MOTOZAKE』の生みの親でもある名門の『日比谷Bar』さんとご縁があったことから、石焼きジャムとうちのお酒をプロのバーテンダーに送ってレシピを作っていただきました」。

こうして完成した「山形カクテルふるふるラ・フランス」。よく冷やしてから、シェイカーのように振って飲めば、まるでバーにいるような雰囲気を味わうことができます。このユニークなアイデアが評価され、2018年の「新東北みやげコンテスト」で特別賞に輝きました。「賞をもらってから酒屋さん、お土産屋さんからお問合せをいただいて取り扱い店が増えたんです。この春から東京のアンテナショップでも取り扱いをいただくようになったんですよ」と、加藤さんは笑顔をのぞかせます。

現在は、りんごフレーバーもリリースし、お客さまからの評判もとてもよいのだそう。加藤さんに今後の展望を伺うと「山形はデラウェアの産地なので、ぶどうでぜひ作りたいですね。ジャムになる果物ならなんでも試してみたいです。一度さくらんぼも作ってみたのですが、とても価格が高くなってしまうので、いずれプレミアムラインでさくらんぼも出せたらと考えています」と目を輝かせていました。

ところで、2019年6月18日に山形県で観測史上最大の震度6弱を観測した「山形県沖地震」。この地震によって、加藤嘉八郎酒造も大きなダメージを受けました。「東日本大震災、中越地震でも酒瓶が割れることがなかったので、大丈夫だと思って倉庫に行ったらたくさん割れて崩れていたんです。一升瓶換算で25万本分のストックがあったのですが、そのうちの4万本弱が倒れたり崩れたりしてしまいました。20人がかりで出荷庫を1週間かけて掃除して、出荷の準備に入ったタイミングで、地元の酒屋さんや県内外の卸業者さんが来てくれて。鶴岡市のほうでも市長が視察に来てくれて、ボランティアを要請してくれました。市のボランティア、有志、お取引先。みなさんのご協力を得て、8月上旬に割れたお酒の片づけが終わりました。みなさんから支えていただいて商売させていただいているんだなと本当に感謝しかありません」。

写真:加藤嘉八郎酒造のみなさん。それぞれが、プロとしてきっちり仕事をこなします
多くの人たちの支えの中、「山形カクテルふるふる」で新たなファンを得て裾野を広げていく加藤嘉八郎酒造。加藤さんは「『ふるふる』はもちろん、まだまだ『大山』を知らない方がたくさんいるので、多くの人に知っていただいてその味を楽しんでいただけるよう、いいお酒を造り続けていきたいです」と話します。

写真:夏は瓶のまま凍らせてシャーベットに。すっきりした味わいの大人のデザートになります

写真:「山形カクテルふるふる ラ・フランス」を鍋にかけ、バターと塩を加えて煮詰めてフルーツソースに。メカジキなど、魚のソテーとの相性が抜群です

写真:「山形カクテル りんご」をソースに。こちらも鍋にあけ、バターと塩を加えて煮詰めるだけ。家で作るポークソテーが、高級フレンチレストランの味になります
この先、どんなフレーバーがラインナップされるのかとても楽しみな「山形カクテルふるふる」。日本酒好きな方やカクテル好きな方はそのままで。未成年の方は、ぜひお料理アレンジで楽しんでみてはいかがでしょうか。
加藤嘉八郎酒造株式会社
住所:〒997-1124 山形県鶴岡市大山三丁目1-38
TEL:0235-33-2008
URL:http://katokahachiro.web.fc2.com/index.html

撮影/堀田 祐介
東北大学法学部卒業後、仙台市内の商業写真撮影会社に就職。写真の道に進む。アシスタントを経てカメラマンとなり、物撮、人物撮影など、写真全般にわたり様々な仕事をこなしながら10年勤務。その後準備期間を経て独立、現在はフリーランスとして、プロバスケットボール・仙台89ERSオフィシャル(初年度から現在まで。来季で15季目)のほか、雑誌媒体の取材(街ナビプレス・仙臺いろはマガジン・ウォーカー・るるぶ)、商業写真撮影、番組用写真撮影と各方面で活躍。